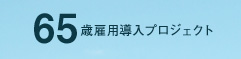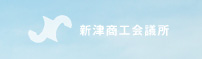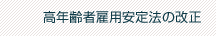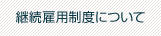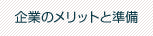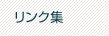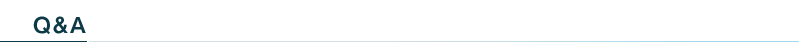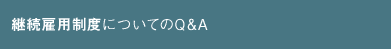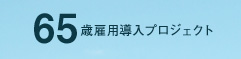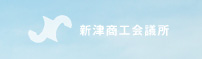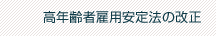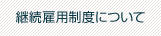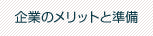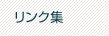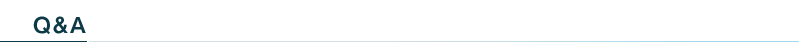| | 平成18年4月1日以降当分の間、60歳に達する労働者がいない場合でも、継続雇用制度の導入等を行わなければならないのでしょうか? |
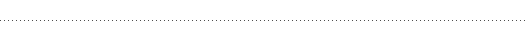 |
 | | 法においては、事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の制度導入を義務づけているものであるため、当分の間、60歳以上の労働者が生じない企業であっても、平成18年4月1日以降、 65歳(年金支給開始年齢)までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置を講じていなければなりません |
 |
 | | 継続雇用制度を導入していなければ、平成18年4月1日以降の60歳定年による退職は無効となるのですか? |
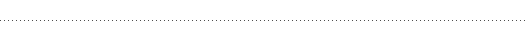 |
 | | 法においては、事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の制度導入を義務づけているものであり、個別の労働者の65歳までの雇用義務を課すものではありません。したがって、継続雇用制度を導入していない60歳定年制の企業において、平成18年4月1日以降に定年を理由として60歳で退職させたとしても、それが直ちに無効となるものではないと考えられますが、適切な継続雇用制度の導入等がなされていない事実を把握した場合には、法違反となりますので、公共職業安定所を通じて実態を調査し、必要に応じて、助言、指導、勧告を行うこととなります。 |
 |
 | | 継続雇用を希望する者について、定年後、子会社やグループ会社へ出向させ、出向先において65歳までの雇用が確保されていれば、親会社として高年齢者雇用確保措置を講じたものとみなしてよいでしょうか? |
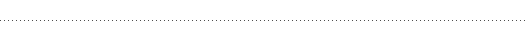 |
 | |
法第9条の継続雇用制度については、定年まで高年齢者が雇用されでいた企業での継続雇用制度の導入を求めているものですが、定年まで高年齢者が雇用されていた企業以外の企業であっても、両者一体として1つの企業と考えられる場合であって、 65歳まで安定した雇用が確保されると認められる場合には、第9条が求める継続雇用制度に含まれるものであると解釈できます。 具体的には、定年まで雇用されていた企業と、継続雇用する企業との関係について、次の(1)及び(2)の要件を総合的に勘案して判断することとなります。
| (1)会社との間に密接な関係があること(緊密性) |
| 具体的には、親会社が子会社に対して明確な支配力(例えば、連結子会社)を有し、親子会社間で採用、配転等の人事管理を行っていること。 |
| (2)子会社において継続雇用を行うことが担保されていること(明確性) |
具体的には、親会社においては、定年退職後子会社において継続雇用する旨の、子会社においては、親会社を定年退職した者を受け入れ継続雇用する旨の労働協約を締結しているまたはそのような労働慣行が成立していると認められること
|
|
 |
 | | 「本社の定年は60歳で、定年後は子会社で派遣労働者として継続雇用される」という制度を導入した場合は、継続雇用制度を導入したということでよいのでしょうか? |
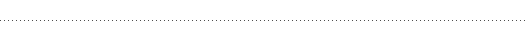 |
 | |
法第9条の継続雇用制度については、定年まで高年齢者が雇用されていた企業での継続雇用制度の導入を求めているものですが、定年まで高年齢者が雇用されていた企業以外の企業であっても、両者一体として1つの企業と考えられる場合であって、 65歳まで安定した雇用が確保されると認められる場合には、第9条が求める継続雇用制度に含まれるものであると解釈できます。 具体的には、定年まで雇用されていた企業と、継続雇用する企業との関係について、次の(1)及び(2)の要件を総合的に勘案して判断することとなります。
| (1)会社との間に密接な関係があること(緊密性) |
| 具体的には、親会社が子会社に対して明確な支配力(例えば、連結子会社)を有し、親子会社間で採用、配転等の人事管理を行っていること。 |
| (2)子会社において継続雇用を行うことが担保されていること(明確性) |
| 具体的には、親会社においては、定年退職後子会社において継続雇用する旨の、子会社においては、親会社を定年退職した者を受け入れ継続雇用する旨の労働協約を締結しているまたはそのような労働慣行が成立していると認められること。 |
また、その子会杜が派遣会社である場合は、継続雇用される労働者について、「常時雇用される」ことが認められることが必要であると考えられます(派遣先がどこかは問いません。)具体的には、次のいずれかに該当する限り「常時雇用される」に該当すると判断されます。
(1) 期間の定めなく雇用されている者
(2) 一定の期間(例えば、2ヵ月、6ヵ月等)を定めて雇用される者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上(1)と同等と認められる者。すなわち、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者または採用 (再雇用)の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者
(3) 日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されて事実上(1)と同等と認められる者。すなわち、(2)の場合と同じく、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者または採用(再雇用)の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者
なお、雇用保険の被保険者とは判断されないパートタイム労働者であっても、 (1)から(3)までのいずれかに該当すれば「常時雇用される」と判断されます。 |
 |
 | | 継続雇用制度について、定年退職者を再雇用するにあたり、いわゆる嘱託やパートなど、従来の労働条件を変更する形で雇用することは可能ですか?その場合、1年ごとに雇用契約を更新する形態でもよいのでしょうか? |
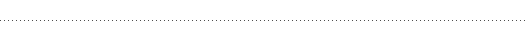 |
 | |
継続雇用後の労働条件については、高年齢者の安定した雇用を確保するという法の趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で、フルタイム、パートタイムなどの労働時間、賃金、待遇などに関して、事業主と労働者の間で決めることができます。
1年ごとに雇用契約を更新する形態については、法の趣旨にかんがみれば、年齢のみを理由として65歳(年金支給開始年齢)前に雇用を終了させるような制度は適当ではないと考えられます。 したがって、この場合は、
(1) 65歳(年金支給開始年齢)を下回る上限年齢が設定されていないこと
(2) 65歳(年金支給開始年齢)までは、原則として契約が更新されること
(ただし、能力など年齢以外を理由として契約を更新しないことは認められます。)
が必要であると考えられますが、個別の事例に応じて具体的に判断されることとなります |
 |
 | | 平成18年3月31日以前に60歳定年で退職となった者を、その後、1年契約で再雇用した場合、改正法施行時には、この者は61歳となっていますが、その場合は、この者も対象とする制度を導入しなければ、法違反となるのですか? |
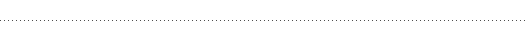 |
 | | 法第9条は、定年の対象となり離職することとなる高年齢者を対象とした継続雇用制度の導入等の措置を平成18年4月1日以降講ずることを義務づけているものであることから、平成18年4月1日前に定年に達した者を対象としないことは高年齢者雇用安定法に違反とはいえません |
 |
 | | 60歳の誕生日で定年としている企業において、平成18年4月1日からは62歳までの、平成19年4月1日からは63歳までの高年齢者雇用確保措置を講ずることとした場合、平成18年4月1日から平成19年3月31日までに60歳の誕生日で定年退職する者については、 62歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となるのでしょうか?それとも63歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となるのでしょうか? |
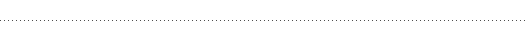 |
 | |
平成18年4月1日から平成19年3月31日までに60歳の誕生日で定年退職する者については、 62歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となりますが、平成19年4月1日以降も引き続き雇用されていれば、当然、63歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となります。
参考
高年齢者雇用確保措置の実施義務化の対象年齢は、以下のとおり、年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げスケジュールにあわせ、平成25年4月1日までに段階的に引き上げていくこととしています。
平成18年4月1日〜平成19年3月31日 62歳
平成19年4月1日〜平成22年3月31日 63歳
平成22年4月1日〜平成25年3月31日 64歳
平成25年4月1日以降 65歳 |
 |